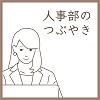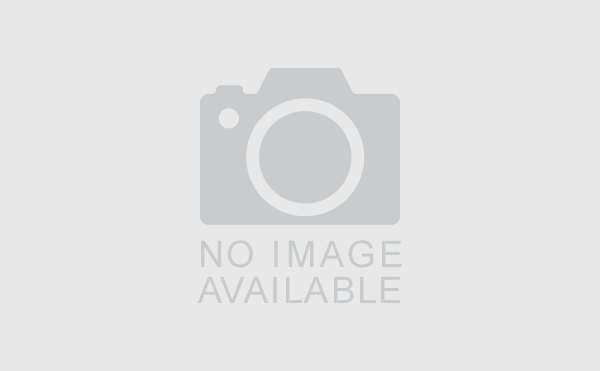異年齢保育って見たことありますか?
みなさんこんにちは。
社会福祉法人フィロスの理事をしてます本多です。
これまでは就職活動に関する記事を中心に投稿してきました。
今回少し趣向を変えて、フィロスの多くの園で採用している異年齢保育について記事を書きたいと思います。
さて、みなさんは異年齢保育を見たことがありますか?
まだまだ導入していない園も多いと思いますので、実習なんかでも見る機会がもしかしたらない方も多いのではないでしょうか?
日本教育新聞でのこんな記事がありました。
こちらもぜひ合わせてお読みください。
今回の記事を読んでいただき、一回見てみたいなと思っていただけたら嬉しいです。
そもそも異年齢保育って何?
異年齢保育とは、複数の学年が一緒に過ごすことをいいます。
複数の学年の組み合わせとしてはいくつかパターンがあります。
- 3〜5歳児が一緒に過ごす
- 0〜2歳児が一緒に過ごす
- 0、1歳児が一緒に過ごす
- 2〜5歳児が一緒に過ごす
フィロス内でもおおよそこの辺りに分類が収まります。
中には0〜5歳まで一緒に過ごしている園があるということも聞きます。
これはそれぞれの施設の考え方によるので、各園を自分の目で見るといいと思います。
なんで異年齢保育を導入しているの?
異年齢保育を取り入れることによるメリットは大きく「子ども」と「職員」に分けて考えることができます。
子どもにとって良い点
- 子ども同士が互いに学び合う関係(大人が手や口を出さない)
- クラスで活動することによる制限からの解放
- 発達の違いを感じ取り年下の子を気に掛ける姿が見られる など
わかりやすいのはこの辺りがあると思います。
年下の子が年上の子がやっている姿を見て真似してやってみる。
↓
試行錯誤して何度もチャレンジ
↓
できるようになる
このような姿が見られます。
また、何か困っている年下の子がいたら、年上の子が気に掛ける姿も良く見られます。
ここに大人が介在しなくても子どもたち同士で色々と解決していくのです。
そこに成長する余白が生まれると考えています。
職員にとって良い点
- 幼児でも複数担任で保育をすることが可能になる
- 休みや休憩など、担任に依存しなくても保育を行うことができるようになる
- 保育の力が付く など
幼児クラスになると1人担任が多いと思います。
異年齢保育を取り入れる場合、多くは3〜5歳児の担任として複数人配置することになります。
その結果、一人担任の時より仲間がいるため、心理的なハードルが下がると考えます。
その結果、休み(有休など)や休憩などで教室から離れても、誰かしらがこの集団のことを理解している保育士がいるという環境を保つことができるのです。
一人担任の心理的プレッシャーとして休みや休憩が取りにくくなるというものがあります。
それが解放されることで、また新たに子どもたちに向き合うことができるようにもなると考えます。
クラスとかどうなってるの?担任は?
クラスはどうなっているのか。また担任などはどうなっているのかという疑問も出てくると思います。
これも様々な方法がありますのでいくつか紹介します。
①縦割りグループでクラス分け&担任
②学年ごとにクラス、担任を設置し、日頃の生活が異年齢
大きく分けると以上のような方法となります。
この辺りの違いを現場で聞いてみると自分はどういう方法が良さそうかという判断軸になるかもしれないですね。
学年ごとの活動はないの?
結論としては学年ごとの活動もあります。
わかりやすいところだと、就学前の年長さんです。
就学を意識した活動も取り入れていく点でここは学年で活動する時間を設けたりします。
なので、100%異年齢が正解。学年ごとはダメということではなく、保育をするにあたって意図があるかどうかが大切なのです。
その辺りは「一斉保育」と「自由保育」でも言えることですが、プロの保育士が保育をするにあたって「なぜそれをやるのか?」と言えることはとても大切なことです。
最後に
異年齢で保育をすることはとても難しいことです。
発達段階が違う集団が一緒にいることで、整える環境をどのようにしたら良いかは常に悩みポイントです。
だからこそ保育が楽しくなるし、子ども視点で保育を行い続けやすい環境にもなります。
異年齢を難しく考えるのではなく、そもそも同じ学年でも月齢で考えれば異年齢なのです。
その違いの幅が広いか狭いかであって、「個々を見る」⇄「集団を見る」は行き来するのが保育です。
ぜひ興味を持った方は職員ができるだけ「手や口を出さない保育」を体験してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。

社会福祉法人フィロス理事兼経営企画室長
採用に関すること。
保育所運営に関すること。
研修に関すること。
働きやすさに関すること。
こんなことをやっています。